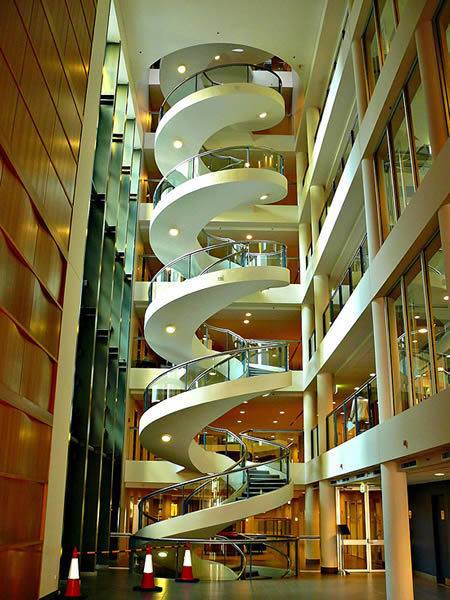JJC運営パートナーの伊藤誠です。
私の職業はファイナンシャルプランナーです。
よく「いくらお金を持っていれば良いか」
と聞かれますので、この点について
今回書いてみたいと思います。
今回はお金のお話です。

これは、以外と簡単で結論は65才時点で
いくら持っていれば良いかを計算することです。
人により、答えが大きく異なります。
まず大事なことは
・我が家が65才からいくら年金を
受給できるかを知ることです。
おおよそで言えば20才から40年間
国民年金に加入する人は年間で
80万円の受給になります。
20才から40年間厚生年金(会社員)に
加入する人はおおよそ年間で
180万円の受給になるでしょう。
そこで、モデルケースとして
1. 夫婦で年間180万円受給する世帯
2. 夫婦で年間240万円受給する世帯
を例にとって計算してみます。
前提は
・90才まで生きる(ちなみに日本人の
女性は2人に1人は90才を超えるという
統計結果がでています)
・月に使うお金は夫婦2人で30万円と
仮定します(これは標準的な金額です。
生きるための最低衣食住等は月に16万円+
夫婦2人のおこずかい その他が14万円と
考えてください)
1. 夫婦で年間180万円受給する世帯は
月に直すと月15万円となります。
ということは月30万円使うと15-30で
15万円の赤字になります。
この15万円の赤字が65才から90才まで続くと
15万円×12ヶ月×25年=4500万円
ということで、65才時点で4500万円
持ってなければなりません。
2. 夫婦で年間240万円受給する世帯は
月に直すと月20万円となります。
ということは月30万円使うと20-30で
10万円の赤字になります。
この10万円の赤字が65才から90才まで続くと
10万円×12ヶ月×25年=3000万円
ということで、65才時点で3000万円
持ってなければなりません。
ところが
2. 夫婦で年間240万円受給する世帯が
月20万しか使わないとすると、65才時点で
貯金は0でも良いということになります。
しかし、これではほとんど遊びにいけないし、
外食もできないし、孫におこずかいを
あげられないかもしれません。

いかがでしょうか。
もう一つ大事なことがあります。
この計算には65才以降家賃や
住宅ローンの支払いがないことが
前提となっています。
みなさんは、65才以降の年金受給はいくらで、
月ご夫婦でいくら使われるでしょうか。
伊藤 誠
人生設計実現パートナー
私の職業はファイナンシャルプランナーです。
よく「いくらお金を持っていれば良いか」
と聞かれますので、この点について
今回書いてみたいと思います。
今回はお金のお話です。

これは、以外と簡単で結論は65才時点で
いくら持っていれば良いかを計算することです。
人により、答えが大きく異なります。
まず大事なことは
・我が家が65才からいくら年金を
受給できるかを知ることです。
おおよそで言えば20才から40年間
国民年金に加入する人は年間で
80万円の受給になります。
20才から40年間厚生年金(会社員)に
加入する人はおおよそ年間で
180万円の受給になるでしょう。
そこで、モデルケースとして
1. 夫婦で年間180万円受給する世帯
2. 夫婦で年間240万円受給する世帯
を例にとって計算してみます。
前提は
・90才まで生きる(ちなみに日本人の
女性は2人に1人は90才を超えるという
統計結果がでています)
・月に使うお金は夫婦2人で30万円と
仮定します(これは標準的な金額です。
生きるための最低衣食住等は月に16万円+
夫婦2人のおこずかい その他が14万円と
考えてください)
1. 夫婦で年間180万円受給する世帯は
月に直すと月15万円となります。
ということは月30万円使うと15-30で
15万円の赤字になります。
この15万円の赤字が65才から90才まで続くと
15万円×12ヶ月×25年=4500万円
ということで、65才時点で4500万円
持ってなければなりません。
2. 夫婦で年間240万円受給する世帯は
月に直すと月20万円となります。
ということは月30万円使うと20-30で
10万円の赤字になります。
この10万円の赤字が65才から90才まで続くと
10万円×12ヶ月×25年=3000万円
ということで、65才時点で3000万円
持ってなければなりません。
ところが
2. 夫婦で年間240万円受給する世帯が
月20万しか使わないとすると、65才時点で
貯金は0でも良いということになります。
しかし、これではほとんど遊びにいけないし、
外食もできないし、孫におこずかいを
あげられないかもしれません。

いかがでしょうか。
もう一つ大事なことがあります。
この計算には65才以降家賃や
住宅ローンの支払いがないことが
前提となっています。
みなさんは、65才以降の年金受給はいくらで、
月ご夫婦でいくら使われるでしょうか。
伊藤 誠
人生設計実現パートナー