「茶遊庵」の案内人 山﨑小夜でございます。
やわらかな緑と小鳥のさえずりに
誘われて、2泊3日の四国めぐりの
旅にでました。
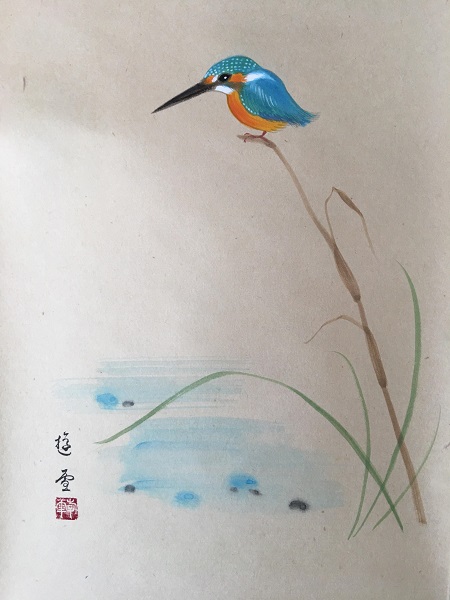
東京=岡山=高松と早いもので
昼頃には着きました。
それから、「ことでん」の
1日フリーきっぷを買い琴平まで直行。
名物讃岐うどんで腹ごしらえをし、
金比羅宮の階段をお年だからと
言いわけもいいつつ途中で引き返し、
両側に立ち並ぶお店さんで
お茶の干菓子にと阿波和三盆を買いました。
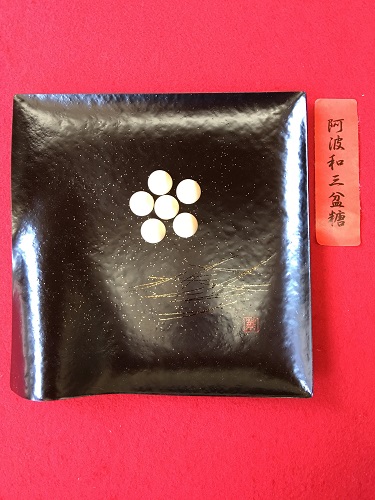
*阿波和三盆糖:徳島と香川県の一部で栽培。
この地方のサトウキビは「甘蔗(かんしょ)」
と呼ばれ背が低い品種です。
1日目の最終見どころ、栗林公園では
根上り五葉松を見、理平焼をみて
宿へと向かいました。

*理平焼:香川県高松市で焼かれる陶器で、
初代高松藩主松平頼重が京都の
陶工森島作兵衛を招き焼かせたお庭焼き。
2日目は高松港から小豆島へ
レンタカーをかり小豆島巡りの始まりは、
エンジェルロード歩き、

なぜか?多いお醬油さん
*小豆島醬油:醬油作りの始まりは
約400年もの昔、当時、小豆島は良質な
塩の産地であり地中海地方によく似た
温暖な気候風土が醬油作りに適し、
海運業が盛んだったことなどから醬油の
島へと発展してきたとのこと。
次はオリーブ公園、高台にあり
眺めは最高、残念ながら
花は咲いていませんでした。
地方の方が、
「日本でオリーブ栽培に成功したのは
小豆島だけ」と鼻高々でしたが、
小豆島産のオリーブはお値段が
良すぎで「お土産」には不向き?かな。

宿に帰り、ツルツル温泉に入り、
なんとも贅沢な1日でした。
3日目の朝の忙しいこと。
大阪城残石記念公園で資料館を見学。
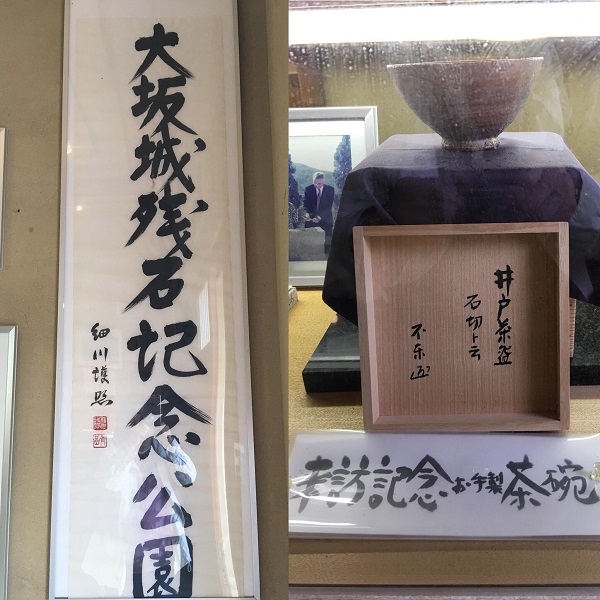
四国フェリーで土庄港から新岡山港に
到着しました。
岡山城と後楽園を散策。
旭川から引いて作り上げた
曲水は見事でした。
この素晴らしい庭園の曲水に
盃を浮かべて詩歌を読み
披講されたのでしょうか。

平成30年 皐月
茶 遊 庵
案内人 山﨑小夜
やわらかな緑と小鳥のさえずりに
誘われて、2泊3日の四国めぐりの
旅にでました。
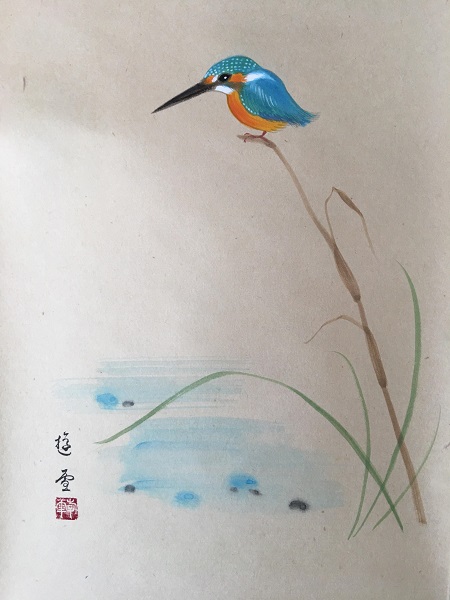
東京=岡山=高松と早いもので
昼頃には着きました。
それから、「ことでん」の
1日フリーきっぷを買い琴平まで直行。
名物讃岐うどんで腹ごしらえをし、
金比羅宮の階段をお年だからと
言いわけもいいつつ途中で引き返し、
両側に立ち並ぶお店さんで
お茶の干菓子にと阿波和三盆を買いました。
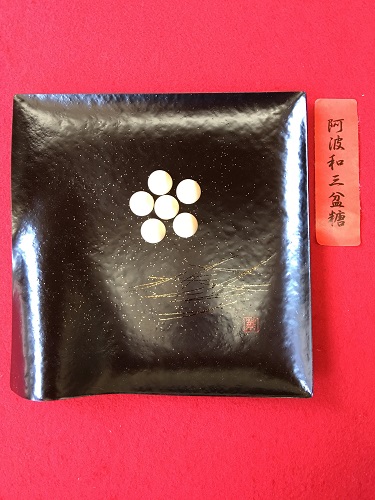
*阿波和三盆糖:徳島と香川県の一部で栽培。
この地方のサトウキビは「甘蔗(かんしょ)」
と呼ばれ背が低い品種です。
1日目の最終見どころ、栗林公園では
根上り五葉松を見、理平焼をみて
宿へと向かいました。

*理平焼:香川県高松市で焼かれる陶器で、
初代高松藩主松平頼重が京都の
陶工森島作兵衛を招き焼かせたお庭焼き。
2日目は高松港から小豆島へ
レンタカーをかり小豆島巡りの始まりは、
エンジェルロード歩き、

なぜか?多いお醬油さん
*小豆島醬油:醬油作りの始まりは
約400年もの昔、当時、小豆島は良質な
塩の産地であり地中海地方によく似た
温暖な気候風土が醬油作りに適し、
海運業が盛んだったことなどから醬油の
島へと発展してきたとのこと。
次はオリーブ公園、高台にあり
眺めは最高、残念ながら
花は咲いていませんでした。
地方の方が、
「日本でオリーブ栽培に成功したのは
小豆島だけ」と鼻高々でしたが、
小豆島産のオリーブはお値段が
良すぎで「お土産」には不向き?かな。

宿に帰り、ツルツル温泉に入り、
なんとも贅沢な1日でした。
3日目の朝の忙しいこと。
大阪城残石記念公園で資料館を見学。
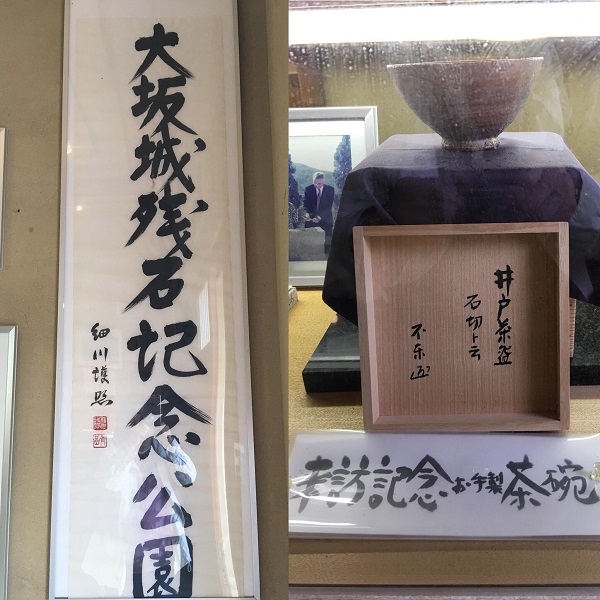
四国フェリーで土庄港から新岡山港に
到着しました。
岡山城と後楽園を散策。
旭川から引いて作り上げた
曲水は見事でした。
この素晴らしい庭園の曲水に
盃を浮かべて詩歌を読み
披講されたのでしょうか。

平成30年 皐月
茶 遊 庵
案内人 山﨑小夜


